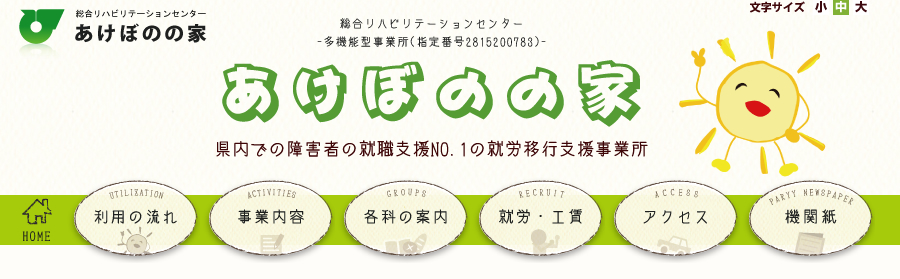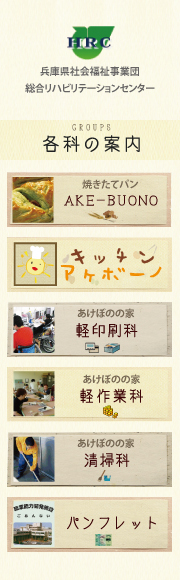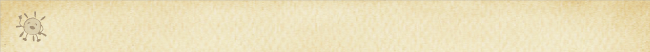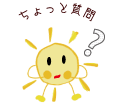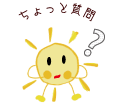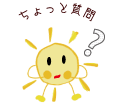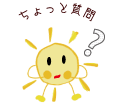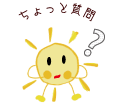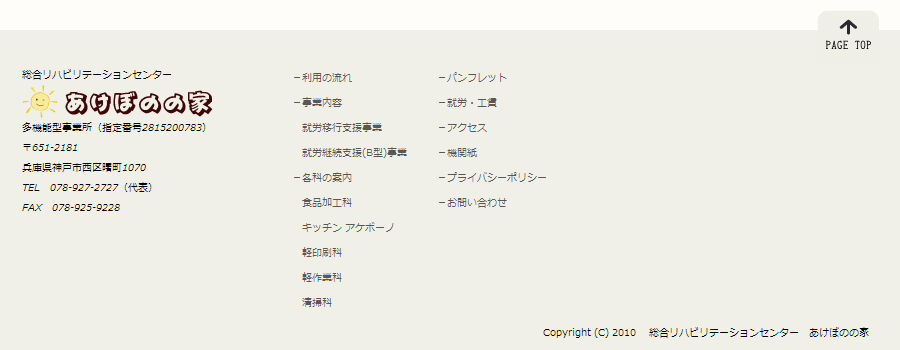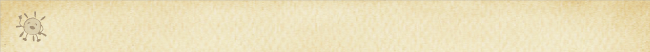
あけぼのの家における就職実績(現状)
平成19年度 就職者4名(内2名が離職)
ケース1
お年寄りの皆さんが生活される施設の清掃作業と、施設内の喫茶コーナーを担当されています。今日も右片手にモップ、左片手にはコーヒーカップを…と忙しく活躍中です。
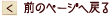
ケース2
事務補助の仕事で縁故関係により採用されたが、障害の影響から事業主が期待する事業を遂行することが難しく、退職に至りました。本人の就職意欲が先走り、本人に適した仕事か否か十分に評価できていなかったことや本人の障害受容が不十分であったこと、仕事先が遠方であったこと等々が積み重なり、就労を継続することが困難となりました。
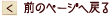
ケース3
トライアル雇用の段階で無断欠勤が続き退職に至りました。就労準備を進める中で、基本的な生活習慣がみついていなかったことが主たる原因と考えます。
トライアル雇用って何?
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業は、障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に、障害者を試行雇用の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業です。
(「障害者の雇用支援のために」より抜粋)
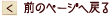
ケース4
お年寄りの皆さんが生活されているグループホームで清掃と事務補助として現在も活躍中です。清掃では施設内のお部屋、廊下、トイレ等々の清掃業務をはじめ外回りの環境整備も行っています。事務補助の仕事では月末・月初を中心に利用者様宛の電気代や食事代などの請求書作成等の事務を行っています。当初は週3〜4日の仕事から始まりましたが、今ではご本人さまの仕事ぶりが認められ5日へ時間数も長くなりました。
今現在も、グループホーム○○で活躍中です。
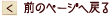
平成20年度 就職者6名(内3名が離職)
ケース5
当リハビリテーションセンター内の障害者専門職業紹介所「みらい」スタッフによる職場開拓にて、職場実習の情報提供があり、本人の意向を確認した上で、職場実習を開始しました。※実習開始にあたっては本人が実習先で混乱する事がないように、或いは受け入れ側の不安軽減のためにジョブコーチ(JC)による支援を活用しました。
本人の頑張りと事業所の受入態勢、JCによる支援等々がうまく組み合わさり、3ヶ月間のトライアル雇用を経て、平成20年6月には本採用となりました。本人は人当たりもよく、周りのスタッフの方々にもかわいがられながら清掃作業や洗濯業務にと真面目に務めてきましたが、元来有していた仕事に対する「責任感」の乏しさから、徐々に欠席する日が目立ち始めるようになりました。適宣、JCによる面接等の支援に入るも、甲斐無く平成22年3月末付けで退職に至りました。(就労期間1年10ヶ月)
ジョブコーチ(JC)って何?
知的障害者、精神障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、きめ細かな人的支援を行います。
〜ジョブコーチによる支援のポイント〜
・雇用の前後を問わず、必要なタイミングで支援を行います。
・障害者が職場に適用できるようジョブコーチを職場に派遣し、直接的・専門的支援を行います。
・障害者自身に対する支援だけでなく、事業主や職場の作業員に対しても、職場の職場適応に必要な助言を行い、また、必要に応じて職務や職場環境の改善を提案します。
・事業所の支援体制を整備し、障害者の職場定着を図ることが目的です。支援の主体を事業所の担当者に徐々に移行していきます。
(「障害者の雇用支援のために」より抜粋)
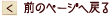
ケース6
当施設の職員が実習先の開拓を進める中で、訪問先の企業さんから障害者雇用考えているとの話があり、本人に白羽の矢が立ちました。ご本人は平成18年2月より当施設の利用を開始し企業内行う長期の就労訓練(グループ就労訓練)にも参加、就職に向けてハローワークでの就職相談等、積極的に就職活動をしているところでした。
早速、株式会社○○での職場実習を開始しました。仕事内容は本人が希望していた、工場での製造業ということもありスムーズに取り組むことができました。勿論、施設の職員も本人が仕事になれるまでは付き添いました。
平成20年5月にはトライアル雇用を開始し、同年8月には本採用となりました。
今も株式会社○○で活躍中です。
グループ就労訓練って何?
事業主(あけぼのの家)が、企業から業務を請け負い、障害者グループに企業内で当該業務の就労を通じた訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者への移行を促進するための事業です。
(「障害者能力開発助成金のご案内」から抜粋)
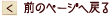
ケース7
「○○大学の環境整備スタッフを障害者枠で応募している」と明石ハローワークから情報提供があり、早速、求人に応募しました。ご本人は過去にグループ就労訓練にも参加し、平成20年2月にはインターンシップ研修にも参加し、積極的に就職活動していました。
平成20年5月に○○大学環境整備スタッフの求人に応募し、6月から採用が決定しました。
もともと仕事に対して熱心なご本人は、○○大学での環境整備ついて一切手を抜くことなく、とにかく真面目に一生懸命頑張られました。しかしながら、体幹に障害があるご本人にとって、毎日、学内の坂道を何度も何度も上がり下りすることは体力的にも厳しいく、1 年を経過した時点で、環境整備スタッフとして働き続けることを諦めねばなりませんでした。(就労期間 1年1ヶ月)
平成21年8月より、当施設の就労移行支援事業を再利用開始され、現在は別の職場へ再就職されました。
ハローワークって何?
就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員等が、地域の関係機関と連携しながら、障害の種類・適度に応じたきめ細かな職業指導、職業紹介、職場定着支援、事業主支援等を行っています。
(「障害者の雇用支援のために」より抜粋)
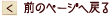
ケース8
「○○大学の環境整備スタッフを障害者枠で応募している」と明石ハローワークから情報提供があり、早速、求人に応募しました。ご本人は平成19年7月には○○事業所での委託訓練(組立加工)を受講し、翌20年1月には○○会社での委託訓練(清掃)を受講するなど積極的に就職活動を行っていました。平成20年5月に○○大学環境整備スタッフの求人に応募し、6月から採用が決定しました。
彼女は今現在も、○○大学の環境整備スタッフとして活躍中です。
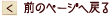
ケース9
平成20年3月まで、企業内で行う長期の就労訓練に参加しながら、施設のリーダー的な役割を担いつつ就職活動を展開してきました。同年7月、当リハビリテーションセンター内の障害者専門職業紹介所「みらい」スタッフより、職場実習の情報提供があり、本人の意向を確認した上で、2事業所について職場実習を実施しました。実習場所ではJCから事業主に以下のことを伝えました。1.ご本人には言語障害があり、 コミュニケーションがとりずらいことや、2.頭で言いようとする言葉と実際にはしている言葉が違うことがあるため確認の配慮が必要であること、3.作業場での姿勢、階段や斜面を歩行する際の注意点等配慮いただきたい点等々。
平成20年11月株式会社○○での採用が決定し、施設利用を終了しました。
平成22年7月に職場訪問した際には、基板プリントの検査業務をおこなっており、会社の上司からも仕事に対する姿勢が大変良いと高く評価を受けていましたが、同年11月に本人が勤務する工場の閉鎖が決定し、12月に退職となりました。(就労期間 2年2ヶ月)
平成23年1月から当施設の就労移行支援事業を再利用開始され、今現在、就職活動中です。
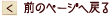
ケース10
平成20年9月、ご本人の地元ハローワークへこまめに通って就職活動していたご本人に、ハローワーク担当職員から「株式会社○○で求人募集している」との情報提供があり、早速、求人に応募しました。
同年11月からトライアル雇用を開始するにあたって、JCの支援を利用すべく調整に入ったのですが、ご本人の地元での就職ということもあり当施設のJCが入るだけでは担いきれないと判断し、地元のJCに応援を依頼し連携支援を行いました。
平成21年2月株式会社○○で本採用となる。
彼は今も、株式会社○○で活躍中です。
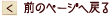
平成21年度 就職者4名(内2名が離職)
ケース11
平成21年の2月、インターンシップ研修(ワークステーション)そして県庁内での職場体験研修に参加し、同年4月には○○医療機関の清掃業務をインターンシップ研修として取り組み、研修先からはコツコツと頑張っていたとの評価をいただく、この時、同医療機関での清掃業務を受託する清掃会社○○で求人 募集しているとの話があり、早速、応募したところ採用が決まり、8月からのトライアル雇用が始まりました。仕事内容は散水や建物内の清掃が中心です。トライアル雇用の期間にも様々な課題が噴出したのですが、雇い主、ハローワーク、JCのよる適切な支援により、一つ一つ克服して11月には正式採用が決定しました。
彼は今現在も、株式会社○○(病院清掃)で活躍中です。
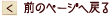
ケース12
平成21年4月から当施設の利用を開始されました。利用開始当初から自分の障害をopenにして働くかcloseにしておくべきか迷っておられたのですが、結果的にはcloseにして一般就労されました。
出来るだけ早く働きたいとの気持ちを持ちで、こまめにハローワークにも求職相談に通っておられました。
平成21年10月 株式会社○○の求人に応募され、採用となる。
元々、短期契約(6ヶ月)の仕事だったので、今は求職活動を行っています。
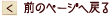
ケース13
平成10年8月から当施設の利用を開始され、一般就労を目指して日々の訓練に参加しながら就職活動を重ねてこられました。
平成21年1月、ハローワーク求職相談に出向いた際に、株式会社○○(A型事業所)が求人 募集しているとの情報提供を受け、早速、応募されました。その結果、平成22年1月から正式採用となり、意気揚々と株式会社○○での仕事に邁進されました。採用当初は、熱心に取り組むことが出来ていたのですが、徐々に仕事のミスが目立つようになり、周りの同僚との対人関係にも課題を呈すようになりました。上司からの指示に素直に応じることが出来ない、仕事に対する責任感が希薄、作業遂行場面での誤った自己判断をしてしまう等々の改善課題が顕著に現れるようになり、約半年間にわたって社長を中心に様々な取り組みにより改善を試みたのですが、結果的には株式会社○○での就労を続けることが困難となりました。
本来、就職前に身につけておくべき職業準備性の不十分さを露呈してしまい反省の多い支援ケースでした。
ちなみに、Aさんは現在、あけぼのの家の就労移行支援を再利用しながら職業準備性の向上を課題に頑張っておられます。
A型事業所って何?
障害者自立支援法に定めるところの就労継続支援A型事業を差し、1.事業所内において雇用計画に基づく就労の機会を提供し、2.それらを通じて一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への意向に向けた支援を行う事業です。
原則として事業主との対象障害者との間で雇用契約を締結しますので、就労(労働)条件は労働基準法等の労働関係法令に基づき定められてます。
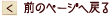
![]()